鍵開け業者の選び方!確認するべきことと流れ
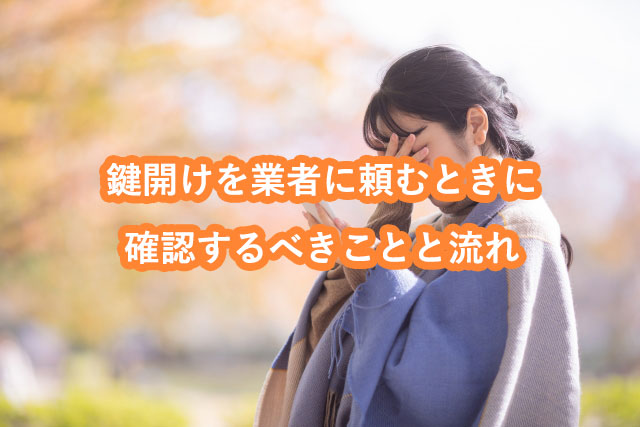
鍵は、人々が安心して暮らして、大事な財産を守っていくうえで、非常に重要なものです。
ただ、鍵はサイズが小さいため、うっかり失くしてしまうこともあるでしょう。鍵を持っていても、突然の故障、いたずらなどの被害によって、開錠できなくなることもあります。
そのようなトラブル時に、助けとなってくれるのが、鍵専門業者です。
鍵専門業者へ連絡すれば、鍵開けのプロが現場まで駆けつけたうえで、開錠、修理、交換などの作業を行ってくれます。鍵のことで困ったら、すぐに鍵業者へ相談してみると良いでしょう。
ただ、業者によって、開錠可能な鍵の種類や技術力、作業料金などが異なるため、依頼前にリサーチが必要です。
そこで本記事では、鍵業者を呼ぶ前に必ず確認すべき点、業者を呼ぶ流れなどについて、わかりやすく解説していきます。
鍵開けの見積り必須!かかる料金は業者によって様々
鍵開けを専門業者へ依頼する際に、必ずやるべきことは、「作業料金の確認」です。作業料金によって鍵屋の選び方も変わってくるでしょう。
仮に、同じ作業内容・作業時間だったとしても、A業者は「2,000円」、B業者「5,000円」、C業者「10,000円」といったように、鍵開けの料金に大きな差が出ることも珍しくありません。
高い料金の鍵業者を選んでしまうと、損してしまうことにもなりかねません。中には、相場価格以上に高額な料金を請求してくるような悪徳鍵業者が紛れていることもあるため注意が必要です。
料金のトラブルを回避するためにも、鍵業者を呼ぶ前にどのくらいの費用がかかるのかをしっかり確認しておきましょう。
作業料金を確認するには
鍵開け作業料金については、鍵業者のホームページ上で調べることができます。
ただ、中には、ホームページで作業料金表を掲載していない業者もあります。もしも、作業料金が不明な時は、直接その鍵業者へ問い合わせてみると良いでしょう。
ほとんどの鍵業者では、問い合わせ用の電話番号、インターネットフォーム、メール、チャットなどから相談を受け付けていますので、自分の都合の良い方法で連絡してみてください。
鍵業者のホームページ等に記載されている料金は、「玄関の鍵開けは4,000円~」といったようにおおよその料金であることがほとんどです。
鍵開けの作業料金は、開錠する鍵の種類、出張エリア、時間帯などによっても、変動することを頭に入れておかなくてはなりません。正確な鍵開け作業料金を知るためには、「見積り」が必須です。
優良な鍵業者のほとんどが、事前の見積りに対応していますので、気軽に問い合わせてみましょう。
作業料金の目安は?
鍵業者を選ぶ際には、作業料金の安さだけに気を取られないように注意しましょう。なぜなら、鍵業者がホームページ上で記載している最低料金には、巧妙なワナが潜んでいる場合もあるからです。
鍵開けの作業料金は、鍵の種類によって変動するのが、一般的です。
たとえば、「南京錠」のようにシンプルな構造の鍵の場合は、比較的簡単に開錠できてしまうため、作業料金が安くなっています。
反対に、「ディンプルキー」のような複雑な構造の鍵の場合は、開錠する際に高度なテクニックや特殊な工具などが必要となります。開錠までに時間がかかることもあるため、作業料金が高めに設定されているケースがほとんどなのです。
このように鍵の構造、開錠の難易度によっても、作業料金が大きく変わることをきちんと理解しておかなくてはなりません。ほかの鍵業者の作業料金と比較して、最低料金が極端に安い場合は、簡単な鍵開けの料金を掲載しているケースが高いため、警戒したほうが良いでしょう。
鍵開けの作業料金のほかにかかる料金を調べる
鍵業者を利用する際には、鍵開けの作業料金以外についても、確認が必要です。
実は、鍵業者に支払う費用は、鍵開けの作業料金のほかにも、様々な費用が必要となります。具体的には、「見積り費」、「出張費」、「破壊開錠代」、「新しい鍵作成代」、「鍵の取り付け代」、「キャンセル代」などです。
この中でも、出張費については、必ず確認しておきたい項目でしょう。
遠方の鍵業者を呼ぶ場合には、ガソリン代、交通費などがかかるため、出張費が高額になりやすいです。事前にどのくらいの出張費が必要なのかを、よく確認しておきましょう。
キャンセル代が発生するかどうかについても、必ず確認しておいてください。
見積り後にキャンセルができないと、万一見積額が相場よりも高い料金だった時に、断りにくくなる可能性があります。安心して料金を確認するためにも、見積り後のキャンセルが可能な鍵業者を選ぶことがおすすめです。
また、玄関の鍵を失くしたと思って鍵業者へ連絡したら、後からポケットから鍵が見つかったというケースも割とよくあります。
あるいは、ダメもとで試してみたら、自力で開錠できてしまったという場合もあるかもしれません。
そのような場合でも、キャンセル代が不要の鍵業者を選んでおけば、無駄なお金を払う必要がなくなるでしょう。
鍵業者はお客様から連絡が入るとすぐに現場へ向かいます。
もしも、途中で鍵開けが不要になった場合は、できるだけすぐに連絡して、キャンセルする旨を伝えるようにしてください。
電話では概算料金になるため現場見積りを確認する
鍵開け料金の見積り方法としては、電話やメールなどがあります。近年は、LINEなどのSNSを利用して、見積りや相談を受け付けている鍵業者も登場するようになりました。
ただ、電話やメール等の見積額は、概算料金となるケースがほとんどです。
概算料金と実際の作業料金には、差があることも多いため、注意してください。確実な作業料金を知るためには、鍵業者に現場まで来てもらい、その場で見積りをもらわなければなりません。
優良な鍵業者の多くは、現場見積りに対応しています。現場で、正確なお見積額をお客様に提示して了承を得た後で、作業に取り掛かる鍵業者を選ぶのが安心です。
反対に、現場での見積りを一切行わずに、すぐに作業に取り掛かる鍵業者は、後から料金のトラブルになる可能性があるため、十分に警戒したほうが良いでしょう。
技術がある鍵業者か確認する
鍵開けの技術力があるかどうかも、鍵業者選びの重要なチェックポイントです。
近年は、防犯上の観点からディンプルキーやロータリーディスクシリンダーなどを取り付ける方が多くなりました。
このディンプルキーは、内部にたくさんのピンが入っており、ピッキングでの開錠が難しいという特徴があります。そのため、ドアスコープから専用の工具を使用してサムターンを直接操作する解錠方法も取り入れられています。
そうした事情を知らなかった場合や開錠技術が低い鍵業者を選んでしまうと、なんでも破壊されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
ディンプルキーは、以前から使われてきたシリンダー錠と比較すると、値段が高いという特徴があります。一旦破壊して、新しいディンプルキーを取り付けるとなると、高額な交換費用も負担しなくてはなりません。
鍵開けの技術力のない鍵業者を選ぶと、無駄な出費を払うことにもなりかねませんので、十分に気を付けてください。
とはいえ、一般の方が鍵開けの技術力を見極めるのは、難しい面もあるでしょう。
まずは、その鍵業者のホームページへアクセスして、施工事例、施工件数などを調べてみることをおすすめします。過去の施工事例や施工件数から、どんな鍵のトラブルに対応できるのかを見極める必要があります。
鍵師技能検定試験、防犯設備士資格認定試験など、鍵や防犯に関する資格を取得しているかどうかも、鍵業者の技術力を知る判断材料となるでしょう。
また、実際に現場に来た作業員の対応を見て、総合的に判断するしかありません。
どうしても不安な方は、事前にSNS、ブログ、口コミサイトなどで、その鍵業者に関する口コミ情報や評判などもチェックしておくことをおすすめします。
鍵開けの業者を呼ぶ流れ
次は、鍵業者を呼ぶ際の流れについても、見ていきましょう。
突然鍵が開かなくなった場合や鍵を紛失してしまうと、誰でもパニックになってしまうことがあります。
慌ててしまうと、冷静な対応ができなくなり、自分の状況を鍵業者に伝えることすら難しくなってしまうかもしれません。
一旦、心を落ち着かせてから、適切な行動を取るようにしましょう。
すぐに鍵業者へ連絡する
最初にやるべきことは、鍵業者への連絡です。
電話、メール、インターネットフォームなどの連絡手段の中から、自分の状況に合わせて最適なものを選んでください。
メールやインターネットフォームだと返信が来るまでに時間がかかることがあります。
真夜中に鍵を失くして困っているといったように、緊急性が高い時は電話で連絡したほうが良いでしょう。
賃貸物件にお住まいの方は、大家さん、もしくは、管理会社への連絡も必要です。
なぜなら、アパートやマンションなど賃貸物件の鍵の持ち主は大家さんとなるため、借りている側が勝手に破壊や交換をすることができないからです。
大家さんが近くに住んでいる場合は、合鍵を貸してもらえる場合もあります。
必ず大家さんや管理会社へ連絡して、判断を仰ぐようにしてください。
状況を伝えたうえで作業料金などを確認しておく
鍵業者へ連絡したら、担当者へ現場の状況を正確に伝えてください。
いつ頃作業に来てもらえるのかや料金についても確認しておきましょう。
鍵業者が現場に到着したらまず見積りをもらう
鍵業者が現場に到着したら、すぐに作業を依頼せずに見積りをもらっておきましょう。
その場で見積額をよく確認して、作業内容や金額に納得できたら依頼するようにしてください。
何か気になる点がある場合は、作業前に必ず確認することが大切です。
作業完了後は料金の清算をする
作業が完了したら、業者と一緒に状況を確認します。
問題がないようであれば、料金を精算して終了です。
緊急で依頼した場合は、現金の持ち合わせがないこともあるでしょう。
夜間だと、銀行やATMが閉まっている可能性も高いです。
クレジットカード払い、請求書払い、銀行振り込み、電子マネーなど、現金以外の決済手段があるかかどうかについても、事前に確認しておくと安心です。
鍵開けにかかる費用相場
鍵開けの相場費用は、鍵の種類、鍵開け場所によって異なります。
大まかな相場費用について、鍵ごとに見ていきましょう。
ギザギザの鍵(ディスクタンブラー錠、ピンシリンダー錠など)
片側、もしくは、両側に山形のギザギザした刻みがある鍵のことです。
「ピンシリンダー錠」、「ディスクタンブラー錠」、「ロータリーディスクタンブラー錠」などがこのギザギザの鍵に該当します。
ギザギザの鍵は鍵穴へ差し込んだ時に、シリンダー内部に入っているピンの高さが合うことで開錠する仕組みとなっているのです。
ロータリーディスクタンブラー錠以外は比較的単純な構造をしていますが、ピッキング対策が施されているものは解錠が難しくなるため、費用も高くなる傾向があります。
そのため、相場費用は、8,000円~15,000円くらいと比較的安いのが特徴です。
ディンプルキー
ディンプルキーは、鍵の表面に小さな丸いくぼみが付いている鍵のことです。
この複数のくぼみがシリンダー内部に入っているピンと合うことで、開錠する仕組みとなっています。
ディンプルキーは、一般的にピンの本数や方向が多く、防犯性の高さにつながっています。
そのため、簡単に合鍵を作ることや開錠することができません。
鍵開けを行う際には、特殊な工具を用意することや高度な技術も必要となります。
プロでないと対応できない場合も多いのです。
そのため、相場費用については、18,000円~とやや高めとなっています。
電子錠
電子錠は、金属製の子鍵を使用しなくても施錠・解錠ができるタイプの鍵です。
カードキーなら、ICチップなどが搭載されており、センサーへかざすことや差し込むことで、開錠が可能です。
他にも、暗証番号タイプやリモコンタイプ、最近ではスマートフォンと連動して施錠・開錠できるタイプもあります。
賃貸物件の玄関のドアのほか、オフィスや店舗の出入り口、ロッカーなどでも用いられることが多い鍵です。
ディンプルキーと同様に、複製されにくく、ピッキング被害にも遭いにくいという特徴があります。
鍵開けをする際には、配線工事など特殊な技術が必要となることから、作業の相場費用が高額となっています。
電子錠の種類によっては、100,000円以上の費用がかかることもあるのです。
鍵開けを依頼する場合は、20,000円~を目安にしておいたほうが良いでしょう。
南京錠
南京錠は、持ち運びができるタイプの鍵です。
ホームセンター、100円ショップなどでも、手軽に入手することができます。
ちょっとした知識があれば、素人でも鍵開けができるくらいにシンプルな構造の鍵であることから、簡易的な防犯対策として用いられています。
鍵業者へ依頼した場合の鍵開けの相場費用は、5,000円~ほどです。
ドアノブ・インテグラル錠
インテグラル錠は、ドアノブと一緒になっている鍵です。
古い住宅の玄関、トイレや浴槽などで用いられてきました。
鍵開けする場合には、相場費用はシリンダーの種類で変動します。
金庫
鍵を紛失したときはもちろん、ダイヤル番号がわからなくなった・暗証番号がわからなくなったなどで開かずの金庫となってしまった事例も多数ございます。
金庫は家庭用から業務用まで多種多様ですので、相場費用も振れ幅が大きいですが、家庭用の小さいものであれば8,000円~です。
車・バイク
外出先で車やバイクの鍵を紛失したり、インロックしてしまったりといったトラブルの事例がございます。
鍵業者へ依頼した場合の鍵開けの相場費用は8,000円~(国産車刻みキー)、鍵作成+鍵開けの場合は15,000円~(国産車刻みキー)となります。
外国産車やイモビライザー搭載キーの場合、高額になります。
鍵を失くした場合は鍵交換も考えよう
ここまで、鍵業者を呼ぶ前に必ず確認すべき点、業者を呼ぶ流れなどについて触れてきました。
最後に、鍵を紛失した場合の適切な対処方法についても、見ていきましょう。
鍵を失くしてしまった時は、鍵開けと同時に新しい鍵へ交換を行うのがおすすめです。なぜなら、誰が失くした鍵を拾って悪用する可能性もあるからです。
万一、住所が特定されてしまった場合は、留守中や就寝中に拾った鍵を使って侵入されるかもしれません。身の安全、大事な財産を守るためにも、その場ですぐに新しい鍵へ交換しておいたほうが良いでしょう。
ただ、新しい鍵へ交換する場合は、別途費用がかかってしまいます。鍵開け費用のほかに、新しい鍵本体代、取り付け費用、交換費用などを用意しなくてはなりません。
特に、ディンプルキーやカードキーなどの防犯性に優れた鍵は、高額な交換費用がかかるため、金銭的に厳しいというケースもあることでしょう。どうしても費用の工面が難しい場合は、後払い決済やクレジットカード払いに対応している鍵業者へ相談してみると良いかもしれません。
もしくは、とりあえず補助錠だけを付けておくという方法もあります。複数箇所に鍵を付けておけば、拾った鍵が悪用された場合でも、開錠することはできません。
空き巣などの犯罪者は、鍵開けの時間がかかることを嫌うため、補助錠があると侵入をあきらめやすいと言われています。すぐに、予算の都合などで、新しい鍵を取り付けるのが難しい場合は、安価な補助錠の取り付けが可能かどうか鍵業者へ相談してみると良いでしょう。
鍵屋キーホースは、鍵開けはもちろん、鍵交換・鍵の取付にも対応いたしますので、お気軽にお問合せください。






